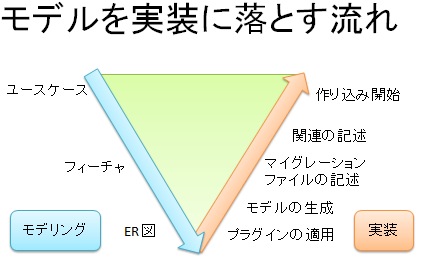昨日Ruby札幌勉強会に参加してきて、RegionalRubyKai(ryの一環として札幌Ruby会議01 を行うことになった過程とか勢いを感じてきました。
雰囲気のわかる資料↓。
この動画の23分27秒あたりに出てくる「 Regional RubyKaigi の御提案 - 角谷さん」あたり参照。
これに被るんだか被らないんだかよくわかりませんが、色々思うことがあったので、地方におけるIT系勉強会について書いてみたいと思います。
なお、おいらがイメージしやすいように、地方のいち都市として札幌を前提に書いていますが、話の趣旨としては全国の各地方都市に当てはまるかと思います。
なお、あまり深く考えて無いので(w)ブレストの結果集まったアイデアぐらいに受け取ってください。
話に出てくる団体の説明
札幌にて勉強会(やそれに類するモノ)とかイベントを1.5月/回ぐらいの頻度で主催している団体。たぶん共通の問題を持ってると思う。
Ruby札幌 〜札幌でRuby絡みをわやわやしているところ。プログラマ・技術者向け。Rubyist向け。
北海道WEBコンソーシアム 〜札幌で主に受託Webシステム・サイト開発絡みをわやわやしているところ。プロデューサー・デザイナ向け。
LOCAL 〜北海道における技術系地域コミュニティの活動をバックアップするためのコミニュティ。OSC2008 Hokkaidoは実質ここのメンバーで運営されていた(?)
他にもアレとソレとコレぐらいのコミュニティが活動してるんだけど、おいら実情をよく知らない。
地方における勉強会の意義
現状に即した地方での勉強会のあり方を考えてみた。
- 絶対的なマス(特定の問題に興味がある人や、その有識者)が少ないので、東京のように「いち企業が公開したサービス」や「いち新技術」に対する突っ込んだ勉強会は成立しにくいのでは? IT 勉強会カレンダー で東京ではどんなことが行われているかあたりを参照。(てか実質的には中の人と話さなければ、かつ「中の人と話して良いよ」と親分と話を付けれるコネがなければ成り立たないと思うので、中の人が居ない地方では成立しない)
- 特にIT関係の勉強会では、ビデオキャストされたり、勉強会のまとめがブログ記事として流れるので、よほど突っ込んだ話か、コネクション目的でなければ、勉強会そのものに参加する必要性は低いのでは? (特にRubyの勉強会などではチャット経由で遠隔地から質問できたりするし)
- 突っ込んだ勉強会に参加する必要がある人(ビジネス上の理由や本流に触れたい人)ならば、東京まで行ってでも実際に参加してきた方がメリットは大きいのでは?(なので、地方ではこれの優先度が低くて良いのでは? もちろん開催できればそれに超したことはないけど)
- 地方ではむしろ、「参加者間の横のつながりや情報共有・雑談(ある程度自立できる技術力を有する人に多い?)」とか「勉強方法や新しい世界への導入(特定分野について勉強したい初心者に多い?)」が主な目的になるのかなぁと思う。
たとえば、おいらの興味範囲として「Amazon EC2&S3&EBS」とか「集合知プログラミング」とか「Hadoop」があるけど、これは北海道では開催できない(開催できたとしても身内のみとか)だと思う。(という具合に諦めている)
地方における勉強会の問題点
Ruby札幌や北海道WEBコンソーシアムの主催者からの話や、LOCALのサイトから鑑みるに、
- 必要な会場設備(電源・無線LAN・スクリーンとプロジェクタなど)を備える施設が少ない。会場確保が大変。
- ビジネス的な理由抜きで協力してくれる企業(研究機関など)が少ない。これがあると会場やセッション内容に幅が出る気がする。
- せっかく勉強会を開いても、それが参加者予備軍に知れ渡っていない(これは地方だけの問題ではないかも)
- 日付決定、会場等確保、案内等の負担が大きい。 このへん参照
- 懇親会の負担も大きいけど、これはイベント終了後に挙手で決めても良いのでは?(予約無しで呑もうなんて甘い? もしくはxx呑み部とかね)
- 有識者を呼びたいけど予算が無い(招待のための交通費・宿泊費など)
- 勉強会の意味合いから見ると、動画配信した方が何かと良い気がする(というか全ての勉強会は動画を配信して欲しい)けど、実際問題として機材が高額だったりノウハウが無ければ配信できない。うまくシェアする仕組みがあればいいんだけど…
- コミュニティに貢献しようという人の絶対数が少ないので、成り行き任せでは運営に協力してくれる人が集まらず、結局コアメンバーの負担が増えて、勉強会が続かなくなる気がする。なので、地方では手伝ってもらうためのフローをあらかじめ盛り込んでおいては?
- 上記全てを内包するけど、主催者側のコアメンバーに負荷が集中(労働力や金銭的)してしまっている。現状自腹&努力?
- 全ての勉強会を知っているわけではないけど、「勉強会」というスタイルである以上、「提供側」と「甘受側w」に分かれると良いことがない気がする。やはり持ち寄り精神が大事じゃないかなぁ。営利目的じゃないんだし。
まとめると、「会場確保」「広報活動と参加者取りまとめ」「活動予算」あたりが問題になるのかな。
特に「時間があったらちょっと来てくださいよ」と簡単に呼べる東京と違って、地理的制約が大きい地方では、有識者を呼ぼうにもまずはカネになってしまう。(Ruby札幌は今までこの予算はどうしてきたんだろう?)
あと、一般的問題点として
- 参加者のスキルや立場によって、勉強会に求めるモノが違う(かも)
があると思う。
地方の勉強会では、どうしてもマスの小ささから、勉強会が乱立できないので、広く浅くになってしまう気がする。
参加者のセグメント分け
たとえばRuby札幌を例にすると
スキルレベル
- ruby初心者(主にRubyを使ってちょっとした業務ツールを作りたい人)
- rails初心者(主にWebアプリを作りたい人)
- 中上級者(作ろうと思えばRubyに限らずそこそこ何でも作れる人)
立場
単純にかけ算の関係ではないけど、6セグメント以上あるのでは?
北海道WEBコンソーシアムだともっといろんな人が居ると思う。(プログラマ・デザイナ・営業・プロデューサー・経営者etc)
テーマ重要
全ての人に満足できる内容を用意するのは無理だと思うので、開催毎にテーマを決めて興味ある人に参加してもらうようにして、毎回初心者でも理解できるセッションと、マニアック(でも聞いていて面白い)セッションを盛り込めばいいのかなぁと思う。
ここ2年くらいで、札幌でも勉強会やイベントなどが増えてきたイメージ(実際には情報共有が出来てきたせいかもしれないけど)があって、さらに増える気もするけど、さすがに毎週勉強会に参加するのは辛いと思うので、あまり興味ない勉強会は参加しないという考えが出てくる。(今のところ、機会が少ないのでどんなものでも全て参加したいと思っている。はず)
そうなってきたとき、広く浅くであっても、参加したことに満足感を得るように、開催毎にある程度の方向付け(テーマ)が重要になってくると思う。
勉強会に何を求める?
たとえば、初心者は
- プログラミング言語やアプリケーションの効率的な使い方(勉強の仕方)
- またはそれによって広がる世界(今は仕組みを理解できなくても、xxを使えるようになると、こんな事ができるようになるよーとか)
に興味があるんだろうし、ある程度スキルがある人なら
- 新技術に突っ込んだ話(特定企業の新サービス・WebAPIや流行ってきた新技術など)
- 昔から存在するけどあまりなじみのない技術に突っ込んだ話(負荷分散、高可用化、仮想化、自然言語処理、全文検索、Linux運用方法、apacheやpostfixなどのデーモンなどとの絡ませ方などなど)
- 同じ分野に興味を持つ人(またはビジネスに繋がりそうな人)と知り合いになる
に興味があるんだと思う。この理論で言えば、Ruby札幌のコアメンバーはRubyの使い方に対して長けている(裏を返せば飽き始めている)ので、純粋にRuby関連の技術ではなく、Rubyと絡めることが可能な「Ruby以外」の技術の方が興味あるんだと思う。他の団体も然り。(や、言い過ぎか?)
※更新 論点から外れたところで誤解を招く表現があったため、削除します
参考として、おいらがRuby札幌や北海道Webコンソーシアムに何を求めるかと言うと、あまり具体的に思い浮かぶモノはないんだけど、強いて言うなら
- 技術者間の友達を作る(コネ含む)
- 特定技術に関する雑談がしたい(情報交換含む)
- 自分がまだ知らない技術に対するとっかかり(刺激)が欲しい
- 自分の興味がある分野を題材にした勉強会ならば、それに対して深く突っ込みたい
って感じかなぁ。
個人的にはフリーランサーしてるのでこういう機会じゃなければ酒を飲めないってのも大きいw
極端な話、勉強会じゃなくてもいいかな。開発集会とかその後の呑み会(+気の合う人と後日メールとかチャット)だけで十分なのかも。
特にオープンソース系の言語だと「いろんな技術のつなぎ役としての言語」という意味が大きいと思うので、Ruby中上級者全員を満足させるのは難しい気がする。逆にそういう人は(地方では)メタ的なものを求めてるんじゃないかなぁと思う。そういう意味では「開いて」「呑めれば」それでいいのかも。(そういう意味でRuby勉強会って難しいよなーとか)
勉強会におけるスタンス
勉強会やコミュニティに貢献することで、自分の生活が貧しくなるのは嫌なので、特定の人が疲れないようにうまく回すには以下のことが必要になると思う。
- 参加者をお客さんとして扱わない。みんなで勉強会を成立させようというスタンスでやる。
- 費用・労働力の分担をフローに盛り込む。
- 参加者を巻き込む。(あ、オープンソースみたいだね)
(野外のジンギスカンパーティに呼ばれたとき、最初から最後まで箸と皿抱えて座っている人は居ないのと同じ考え。北海道にはこの土壌はあるんじゃないでしょうか)
勉強会という特性から考えると、むしろこっちの方が都合の良い事が多い気がする。
具体的には、こんな感じ?
- 必要経費として参加料を徴収する(300円ぐらい?)
- 動画配信できてないコミュニティでも、動画配信できるようにする財源(労働力や機材代)として、サイト上から募金を受けては? (地理的問題や時間の都合で参加できない勉強会で、録画ビデオが存在すれば購入してでも見たいものはたくさんある。ちょっとの募金で金銭的問題はクリアできるなら、おいらは募金すると思う。で、募金と言えば PayPal 。でも実際どうなんだろう?使ったこと無いし。興味はある)
- テーブルやイス、電源周りの用意や後片付けなどは参加者に手伝ってもらう(サイト告知時や終わった後などに声かけする)
- 勉強会で何をしたいかを発言/集約する仕組みを作る。(具体的にはアンケートシステム?)
- スピーカーやってみようかなぁって人も居ると思うので、ライトニングトークや公募スピーカーに向けての時間枠を確保し、Web上などで常時募集する。
- USTREAM を使ったリアルタイム中継や、その後のニコニコへのアップロードとかは、興味のある人を募って手伝ってもらう(ちなみにおいらは興味がある)
- 懇親会は参加者主導にする。好きに行けと。ただし、行きたい人で固まって行こうと。(勉強会の後に親睦会があること自体は告知し、店の予約などはしないが、各自行くかどうかは心に決めて来いと。で勉強会の締めで挙手。10人くらいなら入れるでしょ? おいら呑みたいw)
- 主催者側の肉体的・経済的負担を目に見えるようにする。たとえば、準備するためのタイムテーブルを公開したり、勉強会を開催するために協力してくれた人や、費用(有識者を招いたときの費用も含む)をまとめて、こんなに大変なんだからちょっとで良いから手伝って風に協力を仰ぐ。(そこまでしなくても実情がわかれば手伝ってくれるかも。Webコンの主催者は「部活動」という表現をしていた。的確な表現だと思う)
- 以上をいきなりやれと言われても出来ない(参加者が戸惑う)と思うので、まずは流れを作る。
※北海道Webコンソーシアムは毎回参加料として500円(会員は300円)取ってますが、参加者側としてもあまり苦にはなってないようです。(会場費に使ってますとアナウンスがあるため)
※ただ、お金を取る以上Web上などで会計報告は必要かも知れません
逆に、主催者側で主導すべきは
- 会場確保
- イベント内容や日時を決める
- スピーカー(主に有識者)への根回し・招待・調整(これが一番疲れるんだろうけど、これはコネが必要だからねぇ)
- 会計
ぐらいで、あとは状況によってその場で協力者を募ってもいい気がする。
会場を押さえるノウハウの共有
これをうまく共有できると、開発集会とかSusukino.rb/.js/.mxml/.airとかが勢いで開ける気がする。
実際、Java絡みの勉強会を北海道で開きたいって声もあった気がする。
既存の勉強会のお手伝いも、しやすいかもね。
上記の通り、ある程度なんでも出来る人は、自分の興味範囲を深く突っ込みたいんだと思うので、適切なタイミングで一期一会的に単発の勉強会があってもいいんだと思う。(まぁ、前提として数人集まらないと話にならないので、声かけ出来るぐらいのコネ+開けた広報システムが無いとダメだろうけど)
コンテンツマッチ広告業界について勉強した | IDEA*IDEA あたり参照
要点
- 20人以上入れて、机と椅子があって、電源が取れるところ(ここまで必須)
- 無線LANが使えるところ
- プロジェクターとスクリーンが使えるところ
- あまり高額ではないところ(多少なら割り勘でも負担にならない)
検討すべき他の事項
- 会場はどこかの会社の会議室などを使えないか?(その方が機材が揃いやすい?)
- 札幌駅脇の紀伊国屋の上の小樽商科大学のフロアを使わせてもらえないか?(大学の施設は何かと使いやすい。ただし大学の職員による責任者が必要。パイプ求む)
- 条件を満たす施設はあるけど予算がないということであれば、道や市役所などから補助はもらえないか?(NPO法人化必要?)
- 交通の便はどうか?
- 近くに飲み屋街はあるか?
行政からの補助制度
行政からの補助とか言うと「えーメンドー」とか聞こえてきそうだけど、簡単なら申し込めばいいし、面倒ならスルーで良いと思う。(そこまで本格的に困っているわけでもないだろうし)
予算と広報に関しては、行政の力を借りるのが良い気がするので、補助してくれる制度があるのかどうか調べてみた。
受け入れ体制はありそう。ただ、よくわからんので明日にでも個人的に市役所・道庁へダイブしてくる。(勢い大事。相手してくれるかなぁ?)
質問事項のメモ
- 上記設備を備えた会場はあるか?
- 行政から経済的補助は受けれるか? またそれによって行政側からの干渉はあるのか? 受けれるとしたら条件は?
- 広報活動を行う上で、定期発行物やホームページなどに載せてもらうことはできるか?
- 特定団体の代表ではなく、いち個人として、実現可能性や具体的にどうすりゃいいの?って部分を聞いてきて、叩き台にする。
個人的にはLOCALで受けて、その下に各コミュニティがついて予算をもらう&ノウハウ共有ってのがいい気がする。
ただ、実際補助を受けるとなると色々関係者が動かなきゃならないんだろうし、おいら的にも本気で推しているわけでもないので、さらっと調べて叩き台になればそれでいいかなぁと思っているだけ。役所対応されるとムカッとくるので、明日には「あんなのダメだ」と言い切るかも知れませんw
広報活動
やっぱり参加者(今回は自分の興味に合わないからやーめたーと言ってる人含む)は多い方が面白い。(その分大変だろうけど)
特定団体だけ(縦割り)ではなく、特定地域で行われるイベント全て(横割り?)を集約して、集約したモノをみんなに使ってもらうのが便利だと思う。
これは実質IT 勉強会カレンダー でいい気がする。
ただ、たくさん登録されてて見にくいのでIT 勉強会カレンダー検索 (能動的に絞り込み)、またはこのスクリプトの様なgoogleカレンダーをフィルタリングするプロキシ(のようなもの)を経由して、北海道絡みだけのイベントカレンダーを公開(受動的に絞り込み)して使ってもらうのが良いかも。誰かサーバ資源余っている人設置してみてください。(Herokuでやろうとしたらrobots.txtが邪魔してダメだった。現状ではプロキシ的なものを経由させなければ、googleカレンダーだけではフィルタリング・自動同期できない)
あと、勉強会に参加するような人が見てるかどうかわからないけど、市役所や道庁が出している広報や、道庁・札幌市のHPに勉強会の情報を載せてもらうとかすれば、裾野は広がる気がする。(リンク先が上記特定地域版googleカレンダーになっているのが理想)
お、忘れてた。おいら北海道のIT関係イベントをまとめるコミュニティ(と言えるのか? トラコミュって)を作ったんだった。現時点では意味がないけど、みんなが使ってくれると意味のあるモノになる気がする。(でもマジメに広めようという気はない)
あと、人が集まるであろう所にポスター(までは行かなくても、告知できるもの)を貼るとか、特定スペース占有可能な掲示板的なものを使わせてもらう事って出来ないのかなぁ。たぶん、参加者予備軍(IT関係の会社などに勤めている人とかとか)の大半は、勉強会があること自体を知らないと思う。
知っていて来ないのは良いとして、知らなかったから来ない(知ってたら来てたのに)ってのはとてももったいない気がする。
個人的意見
- みんなが楽しめればそれでいいのでは? (学問的にストイックな内容が含まれてもいいけど、それが主体だと辛いのでは? 意味が無くてもそれが楽しいならいいのでは? OSCでのマラカスコントローラーのように)
- かつ、主催者側も自分が楽しければそれで良いのでは? (あまり参加者の顔色を見ずに、自分の興味範囲を好きなようにしゃべれば良いのでは? おいらなら、みんなのためとか、地域のためとか言ってると、たぶん疲れて嫌になる)
- 基本的に勉強会に参加するだけで楽しいと思うんだけど、主催者側だけが肉体的・経済的に辛いとうまく回らないと思うので、コミュニティ全体として回るような工夫が早急に必要では?(とりあえず受け入れ準備だけでも整えては?)
- 「自分は初心者なので勉強会に参加することで勉強したい」と言う人が多い印象だけど、実際には刺激を受けてモチベーションが向上するぐらいしか、効果がないように思う(そりゃそうだ)。スキルを上げたいなら、ちゃんとまとまっている書籍なりサイトを読んで、ニュースを追って、かつ自分で何かを作り上げてみないとスキルアップはしないと思うから。この「勉強方法を伝える」という意味では、勉強会の中でセッションがあっても良いとは思うけど、最終的にはWeb上にまとまっていた方が使い勝手が良いと思う。
- 逆に自分で勉強してみて、どうもうまくいかない時があると思うので、そんな時に気軽に聞ける場所(SkypeのオープンチャットやIRC、もしくは開発集会)があれば理想かも。現状こういう意味ではあまりうまく機能してない気がする。
- なーんで、プレゼン資料をネット上で公開しない人がいるんだろうねぇ。特定のイベントでしか話さないことに意味がある(金を取ってるとか)とか、その一時期だけしか意味がない(あとは著作権上問題がある)ならわかるけど、ノウハウの固まりみたいなプレゼン資料(パワポとかにまとまっているやつ)を、サイト上で広く公開しない理由がよくわからない。なんの為にプレゼンしたの?みたいな。
- イベントを開くためのノウハウや支援団体(北海道ならLOCAL?)が広く公開・認知されている状態ならば、ちょっと何かやってみようかなぁという人が出てくると思うし、既存の団体(Ruby札幌やWebコン)のイベント内のセッションや、分会となってもいい気がする。「時間だけ確保しといたから好きに使って」みたいな。(主催者側があれこれ考えて疲れちゃうよりよっぽどいい気がする)
- と、いう意味でもっとLOCALが強権と金握って、協力するからどんどん訪ねてきなさいはっはっはーぐらい言っても良いと思う。(現状Webコンとかは未参加だよね)
- 悪影響がないなら、NPO法人化してでも行政から補助を受けた方が(主催者・参加者共に)良いと思う。もっと有名人の話を「北海道で」聞きたいよねぇ。
さて、巻き込もう
おいらはどのコミュニティの運営側の人でもなく、内情や今までの経過を知らないので、上記のようにはならない可能性は十分にあるのですが、まぁ、どうせ外野なので言うだけ言ってもいいだろうとw (徹夜で書いたのであまり現実的ではない話もあるし)
企業の力をもっと使った方がいいとか、カネカネ言うなとか、いろんな意見があると思うので、トラックバックなりコメントなり、電話や呑み会で仲間と話してみてください。
んで、積極的に勉強会に参加してみてください。
おいらはとりあえず、LOCALのMLに参加して、道庁と市役所に行ってこよう。
しまった、増田で書いた方が話題性があったか?!